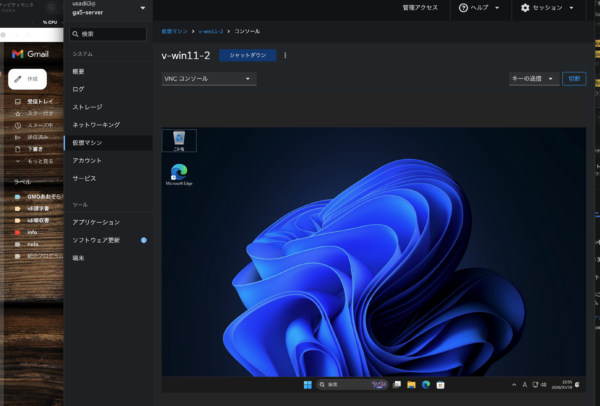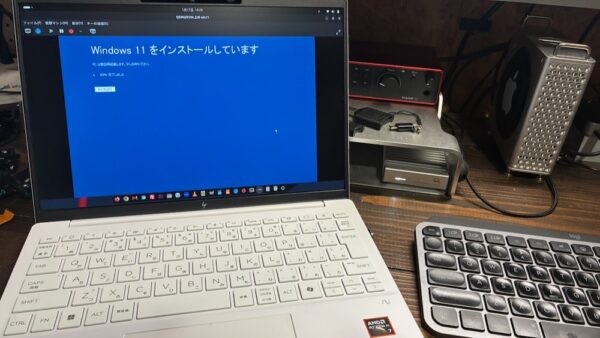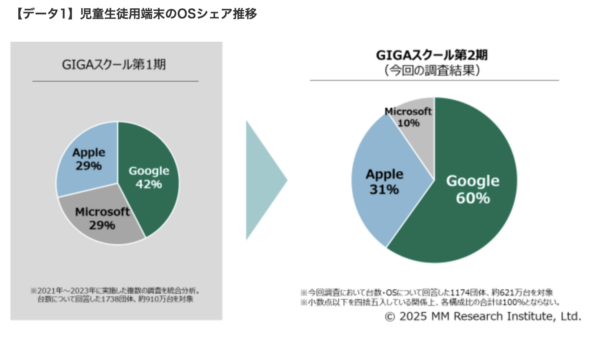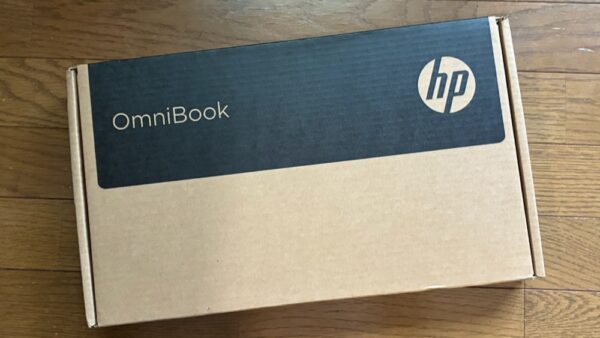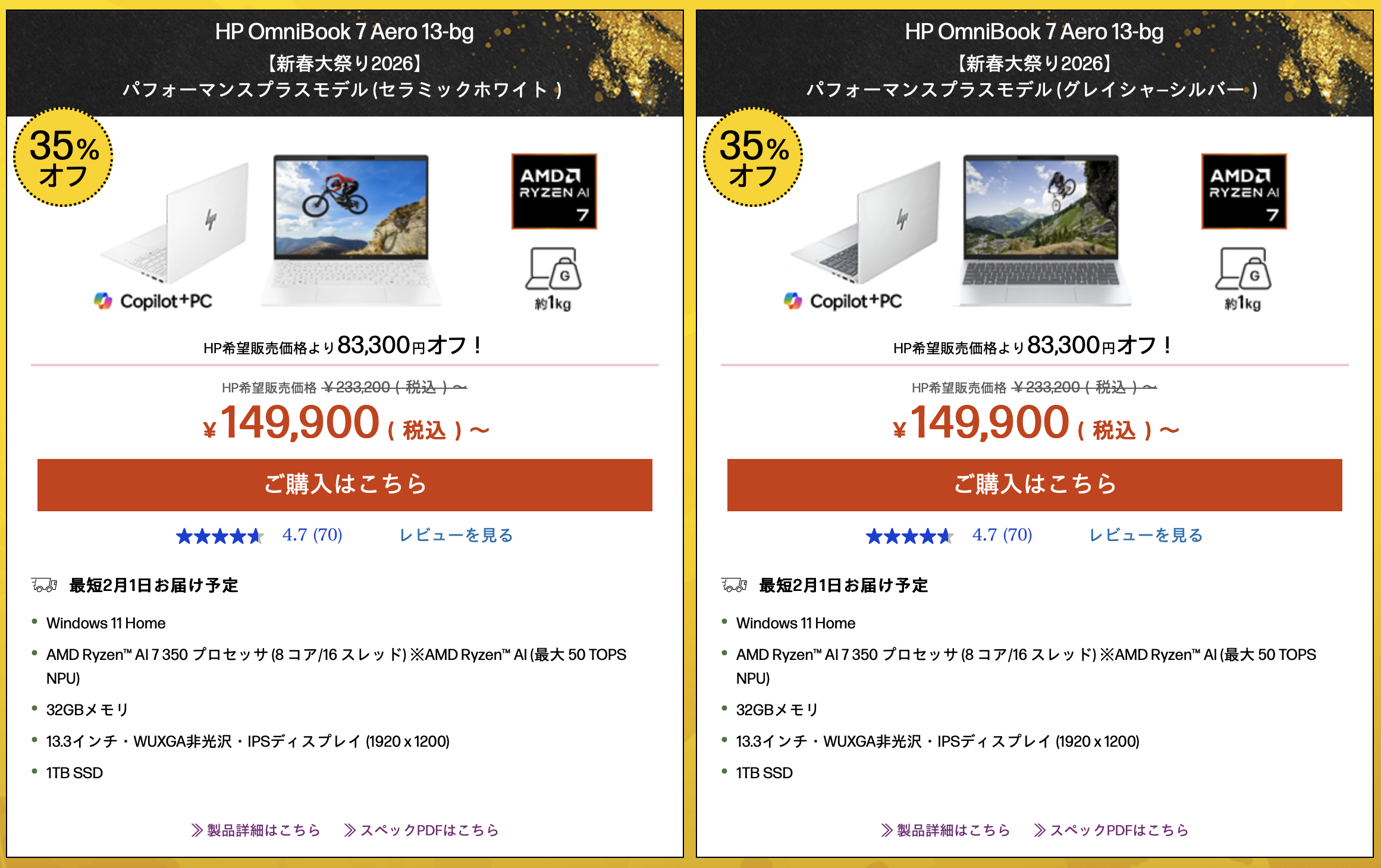【重大】Windows11、アップデートKB5074109が入っているのを見つけたら即アンインストールすべし
Windows11の話題が続いているが、それほどまでに重大なエラーをここ最近立て続けに起こしているMicrosoftなのだ。
さて、問題の「KB5074109」だが1/14に配布され多くのWIndows 11 PCにInstallされているのだが、こいつがかなりヤバい。
- 最悪のパターンは真っ黒い画面に白い文字がでて起動しなくなる
- スリープ後無反応になる
- 真っ黒な画面にマウスだけになる
- 一部のアプリが起動・動作しなくなる
- 電源が切ることもスリープすることも出来なくなる
- Outlookが起動しない
- DropBoxが動作しない
- OneDriveが固まる(デスクトップなどをOneDriveにしてたかたはデスクトップがまっさらな状態になり何も開けない)
- ネットワーク越しのセキュリティ要件を満たす必要のあるような使い方(企業など)がセキュリティが通らず
などなど影響は多岐にわたる。特に古めのPCで影響が出やすいようで特に本来WIndows11の要件を満たしていないPCに裏技でWindows11を入れたようなPCでは顕著なようだが、新しいPCでも起きる可能性はある(あった)。
Microsoftは緊急パッチを1/17と1/24に出したが、1/27時点でいまだ解決していない。現時点で普通に起動して使えている方で「KB5074109」のアップデートがInstallされているのを確認出来た方は起動できているウチに「KB5074109」をアンインストールし、しばらくアップデート更新を止めておくことを強くお勧めする。
// 先述した通り私の周りでも複数台、影響が出たのを確認しました(新しめのPC)